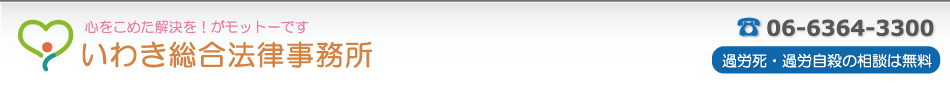勝訴の一審判決を乗り越え、高裁で完全勝利和解──サンマークサービス残業代請求訴訟 弁護士 岩城 穣(民主法律251号・2002年8月)
【1】事案の概要
高橋映美さん(26歳)は、99年7月「サンマーク」(本社・東京)に入社し、大阪支社編集部(従業員数約20人)で、「Nasse」という無料情報誌の広告営業と編集を担当していた。
同社の募集広告では、「勤務時間10時~18時、給与月額20万円以上」となっていたが、実際に入社すると、午後から外回りの営業活動を行い、午後6時ころ帰社した後、編集作業を午後8時、9時、遅い時には11時半まで行っていた。また、写真撮影などが午前中や夜遅く行われることもあり、「直行・直帰」も頻繁にあった。
にもかかわらず、給与は、営業実績によるわずかな「販売手数料」を除けば、20万円の定額で、残業手当はまったく出なかった。
高橋さんは支社長に何度も説明を求めたが、「うちの会社では残業代は払われないことになっている」などと取り合おうとしなかったため、2000年9月末で会社を退職した。
高橋さんは悔しくて悶々としていたが、2001年6月に結成された「労働基準オンブズマン」に相談し、私と田中俊、籾井美恵子弁護士の3人が代理人となり、同年8月、会社に対し、時間外手当と付加金の支払いを求める訴訟を起こした(当初は早出残業分を含めず660時間分を請求したが、その後約700時間分に拡張し、手当額・付加金それぞれ116万円、計232万円の請求とした)。また同年9月、オンブズマンが行った「一斉告訴・告発」の一環として、同社と社長及び支社長を労基法違反で天満労基署に刑事告訴した。
【2】一審での争点と一審判決
一 一審での争点(一審判決自体は明確な整理はしていない)
〔争点1〕実労働時間の把握の仕方
①タイムカードで労働時間を管理している場合、その打刻された始業時刻、終業時刻で労働時間を認定すべきか。
②週休二日制で土曜出勤してタイムカードが打刻されている場合、タイムカードと「時間外勤務許可願」のいずれをもって労働時間を認定すべきか。
③タイムカードが打刻できない「直行・直帰」の場合、事前報告と現場からの電話報告、それを踏まえた月単位の「勤怠報告書」によって労働時間を認定できるか。
〔争点2〕時間外手当の支払義務の有無
①「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)における「労働時間を算定し難いとき」の意義
②営業社員に支給される月額8万円の「営業手当」は、時間外手当の性質を有するか。
二 1審判決の内容
2002年3月29日、大阪地裁(松本哲泓裁判官)は、前記の争点について以下のように判示し、約390時間分の残業手当(約104万円)と遅延損害金、及び認定した残業手当元本と同額の付加金の合計約21万円の支払いを命じた。
〔争点1〕の①について
所定終業時間は午前10時から午後6時までであって、始業開始前の就労について就労命令がなされた事実は認められない。所定始業時刻の15分程度前に出勤するよう指示されていたとしても、これに遅れても遅刻扱いや叱責された事実はなく、朝礼が午前10時から始まることからすると、単に心構えを訓示したものにすぎず、業務命令とはいえない。
終業時刻については、「一般的には、タイムカードに打刻された時刻をもって単にその事実だけからその時刻までの業務指示がなされていたものと推認することはできないが、本件では、原告の就労場所とタイムレコーダーが設置された場所とは近く、業務終了からタイムカードの打刻まで、それほど時間がかかる事情もないことからすると、タイムレコーダーによってタイムカードに打刻された時刻を終業時刻と推認することができる」とした。
〔争点1〕の②について
「時間外勤務許可願」に記載された時間帯を超える時間については、「業務指示がされていない」として、「時間外勤務許可願」記載時間についてのみ労働時間と認めた。
〔争点1〕の③について
「いわゆる直行直帰、すなわち事業所外の就労場所に直接出勤して業務に就き、同所から直接帰宅する場合、始業時刻は、就労場所において業務を開始した時刻と、終業時刻は、業務を終えた時刻と認めるべきであるが、その正確な時間を明らかにするものはないので、午前10時に就労し、午後6時に終業したと認める。」
〔争点2〕の①について
「原告が担当した業務は、格別高度な裁量を必要とするものではなく、事業所外における業務は、前日提出の報告書や当日の打合せで上司に把握されており、その結果も、訪問先における訪問時刻と退出時刻を報告するという制度によって管理されており、……原告が事業所外における営業活動中に、その多くを休憩時間に当てたり、自由に使えるような裁量はないというべきで、事業所を出てから帰るまでの時間は、終業規則上与えられた休憩時間以外は同時間であったということができ……被告による具体的な営業活動についての指揮命令は基本的にはなかったものの、原告の労働自体については、被告の管理下にあったもので、労働時間の算定が困難ということはできない。乙1(注、社員募集広告)は、就労時間として、午前10時から午後6時までと記載しているが、これは、事業所外における営業活動を含んだ時間であることが明白で、……被告も事業所外における営業活動の時間はすべて労働時間として観念していたことが窺われ、この点も、上記判断を裏付けるものというべきである。直行直帰の場合においても、所定労働時間以上を就労したものについては、その営業活動について、被告の管理下にあったことは、直行直帰以外の場合と同様であって、労働時間の算定が困難ということはできない。」
〔争点2〕の②について
「一般的にいえば、営業社員の時間外労働手当を営業手当として固定額で支払うことも、労働基準法所定の割増手当額の範囲内では、有効なものということができるが、乙1によれば、被告は、原告が応募した際における従業員募集において、募集広告に、勤務時間を10時から18時とし、給与を月給20万円以上と記載していたし、雇用の際の原告に対する説明においても、営業手当が時間外賃金としての性質を有するといった説明はされなかったし、営業手当を除いた場合の賃金水準が高くないことを考慮すれば、これが営業社員についてのみ支給されているなどの点を考慮しても、……時間外手当の性質を有するものと認めることはできない。」
三 一審判決の意義と問題点
(1) 一審判決が、事業場内での居残り残業についてタイムカードによる労働時間を認定し、また被告の事業場外労働のみなし労働時間の適用や、営業手当の定額残業手当性の主張を排斥して、時間外手当と付加金の支払いを命じたことは、当然のこととはいえ評価できる。
(2) しかし同時に、一審判決は次のような問題を含んでいた。
ア タイムカードを基準に労働時間を認定ないし推定するという考えをとらず、実際、所定始業時刻前の早出残業を労働時間と認定しなかったこと。
イ 土曜出勤についても、タイムカードがあるにもかかわらず、「時間外勤務許可願」に記載された過少な労働時間しか認めなかったこと。
ウ 直行直帰の場合、始業時刻は就労場所において業務を開始した時刻、終業時刻は業務を終えた時刻と認めるべきであるとしながら、「その正確な時間を明らかにするものはない」ことを理由に、午前10時から午後6時までの就労しか認めなかったこと。
(3) このうち・・・については、労働時間の認定にあたり、使用者の具体的な指揮命令ないし指揮監督をどの程度要求するのか、またタイムカードによる労働時間管理をどのように位置付けるのかという問題と関連する。
使用者の指揮命令の必要性を強調すれば(特に1審判決は、早出残業について「就労命令」まで要求している)、事業場内での居残り・早出残業はもちろん、休日出勤や自宅での持ち帰り残業など、多くの時間外労働に手当は支払わなくてよいことになってしまう。
また、労働者にとっては、自らの労働時間を正確に記録する方法はタイムカードしかなく、これで労働時間が算定されないとすると、使用者の労働時間管理のルーズさをもって労働者に不利益を帰することになり、不当である。
この点、厚生労働省も2001年4月6日付け通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の冒頭で、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している」としているところである。
この点についての判例は分かれている。北陽電気事件判決(大阪地判平成元年4月20日・労判539・44)は「一般に、会社におては従業員の出社・退社時刻と就労開始・終了時刻は峻別され、会社はタイムカードを従業員の遅刻・欠勤をチェックする趣旨で設置していると考えられ……従業員の労働時間を算定するために設置されたものではないと認められる。したがって、同カードに打刻・記載された時刻をもって直ちに原告らの就労の始期・終期と認めることはできない。」とし、三好屋商店事件判決(東京地判昭和63年5月27日労判519・59)は、「(タイムカードの)打刻時間が所定の労働時間の始業もしくは終業時刻よりも早かったり遅かったとしてもそれが直ちに管理者の指揮命令の下にあったと事実上の推定をすることはできない。……タイム・カードによって時間外労働時間数を認定できるといえるためには、残業が継続的になされていたというだけでは足りず、使用者がタイム・カードで従業員の労働時間を管理していた等の特別の事情の存することが必要である」としている。
これに対し、京都福田事件判決(京都地判昭和62年10月1日労判506・81)は「被告はタイムカードによって労働時間を管理していると認められるから、原告らの時間外労働の時間数もタイムカードによって認定することが相当である。」とし、日本コンベンションサービス事件(大阪地判平成8年12月25日労判712・32)は、「タイムカードの打刻が遅刻をチェックする意味しかないからといって、そのことからタイムカードの記載が従業員の労働時間の実態を反映していないということにはならないし、……タイムカードの打刻は継続的に行われ、それがルーズに行われていたとはいえないのであるから……タイムカードに基づいて、原告らが従事した時間外労働時間を算定することができるというべきである。」「タイムカードが、原告らの労働実態に合致し、時間外労働時間を算定する基礎となる以上、タイムカードの記載と実際の労働時間とが異なることにつき特段の立証がない限り、タイムカードの記載に従って、原告らの労働時間を認定すべきである。」と明快に判示している。
我々は、前述の厚生労働省の通達も受けて、この点について積極的な判決を期待したが、1審判決は一般論の立て方も、具体的な認定においても、極めて不十分なものであったといわなければならない。
(4) については、直行直帰の場合、事の性質上タイムカードの打刻は不可能であるが、それをもって労働者に不利益な扱いをすべきでなく、事前・事後の上司の承認手続や連絡体制など、他の合理的な事情によって、実態に即した認定を行うべきである。
四 双方が控訴
一審判決は、請求額の九割以上を認容したが、これらの問題点があったことから、高橋さんはあえて控訴することとし、会社側も控訴したため、舞台は控訴審に移ることとなった。
【3】控訴審での全面勝利和解の成立
一 ところが、双方から控訴理由書が提出され、高裁の第一回期日の二〇〇二年七月一〇日を目前に控えた七月五日、会社代理人から、原告側の請求を基本的にすべて受け入れるので、第一回期日で和解してもらいたい旨の申し入れがあった。
我々としては、前記のような一審判決の不十分点を高裁で正したいという思いもあったが、こちらの請求はすべて呑み、さらに後述のように原告に対する謝罪や、会社の制度改善にも応じるとのことであったので、和解に応じることにした。
二 成立した和解の骨子は、次のとおりである。
(1) 会社は高橋さんに対し、時間外手当の不払いとこれについての対応に問題があったことを認め、謝罪する。
(2) 会社は高橋さんに対し、①~④の合計約248万円を支払う。
①一審原告の請求する未払時間外手当の元本全額 116万円
②うち、原判決の認めた未払時間外手当の元本約104万円に対する和解日までの年一四・六パーセントの割合による遅延損害金 約二八万円
③原判決の認めた付加金の元本 約104万円
④会社は、今後は本件のような事態が起こることのないよう、労働基準法の趣旨に沿い、必要な制度と運用の改善を行うことを約束する。
【4】本件和解の意義と勝因
一 本件和解の意義として、次の点を指摘できる。
(1) 一審判決で認容された、終業時刻についてのタイムカードによる労働時間認定に加え、始業時刻及び土曜出勤についてもタイムカードによる労働時間算定を行わせたこと。
(2) 直行直帰の場合についても、労働時間についての資料がないとして所定時間分しか認めなかった一審判決を乗り越え、実際に働いた労働時間を認めさせたこと。
(3) 事業場外のみなし労働時間制の安易な適用を認めず、また営業手当が時間外労働の性質を有しないとした一審判決の積極面を維持させたこと。
(4) 判決では得られない、原告に対する謝罪と、会社における制度改善の約束をさせたこと。
二 全社的に営業社員に対してまったく残業手当を払わず、一審で徹底的に争っていた会社が、なぜ一転して、制度改善の約束を含む和解に踏み切ったのか。その要因として、次のことが考えられる。
(1) 高橋さんと弁護団が、会社における労働実態を十分に明らかにしたこと。
(2) 会社側の主張を完全に論破し、反論不能に追い込んだこと。
(3)高橋さんの友人や過労死家族の会の人たちを中心に、毎回の法廷を多くの人たちが傍聴したこと。
(4) 労基オンブズマンの活動などにより、サービス残業が社会問題となる中で、一審判決がマスコミに大きく報道され、社会的批判を受けたこと。
(5) 昨年九月の刑事告訴を受けて労基署が社長・支店長と会社を労基法違反で書類送検したことから、このままでは有罪判決が避けられないと判断し、和解によって起訴猶予を期待したと考えられること。その意味で、刑事告訴は十分意義があったといえる。
三 会社の年間の所定労働時間は1740時間であるのに対し、原告の労働時間は2440時間で、その差の約700時間がサービス残業であった。営業社員の中には、高橋さん以上に働かされている社員も多かった。現在過労死が若者や女性にまで広がっているが、その背景にはこのような膨大なサービス残業がある。
サービス残業は労働者の労働力を盗み、健康まで破壊するものであり、違法であり犯罪である。
このことを明らかにするために、たった一人で勇気をもって告訴と裁判を行った高橋さんに心から敬意を表するとともに、労基オンブズマンとして、今後いっそう取り組みを広げていきたい。
(弁護団 岩城 穣、田中 俊、籾井美恵子)
(民主法律251号・2002年8月)