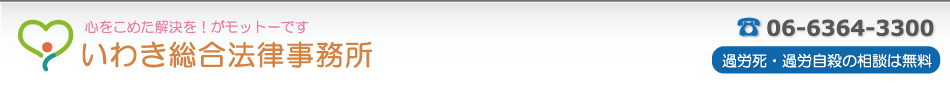1 はじめに
名糖運輸で牛乳などの配送運転手をしていた故西原道保さん(当時46歳)が平成3年2月23日に急性心不全で死亡した事件で、名糖運輸を被告とする民事訴訟、堺労基署長を被告とする行政訴訟が闘われてきているが、昨年1月の行政訴訟1審の勝訴(大阪地裁民事5部、松本哲泓裁判長)に引き続き、本年2月19日、民事訴訟1審(大阪地裁民事15部、中路義彦裁判長)は、被告名糖運輸に対して4600万円余の支払いを命じる勝訴判決を下した。
2 判決のポイント
(1)判決は、故道保さんの急性心筋梗塞による死亡は、7年以上に及ぶ過重労働による慢性的な蓄積疲労に、発症4日前からの新業務による新たな精神的ストレスが加わった結果であるとして、過重業務の継続による蓄積疲労を正面から認めた。
また、会社は故道保さんの業務が過重であったことを容易に認識し得、またこのような過重業務が原因となって虚血性心疾患を発症し、ひいては故道保さんの生命・身体に危険が及ぶ可能性があることを予見し得たのに、業務の量などを適切に調整するための措置をとらなかったことに過失があるとした。
これらの判示では、電通事件、東京海上支店長事件の2つの最高裁判決を意識した記述が随所に見られ、これらの影響が強く窺われる。
(2)故道保さんが年間約40万円分に相当するサービス残業を強いられていたことが証人尋問の中で明らかになったため、その分を年収に加えて逸失利益を計算し直して請求を増額したところ、被告がサービス残業であったことを認めたことから、判決は増額を認容した。サービス残業分が逸失利益算定の基礎に加えられたことの意義は大きい。
(3)他方、判決は、①故道保は1日20本程度の喫煙をしており、また46歳の年齢から考えて喫煙期間は20年以上であったと窺える、②故道保さんも早期に医師の診断を受けるなどして自らの健康を積極的に保持すべく措置すべきであったといえるとして、20%の寄与度減額を行った。
しかし、①については、1日20本程度の喫煙をしていたというだけで寄与度減額を行うのは極めて問題である。しかも、喫煙期間が20年以上あったなどというのは、明らかに証拠に基づかない認定である(会社はもちろん、妻の松子さんさえ知らない)。
②の自己保健義務については、故道保さんの業務の実態からして医師にかかることは極めて困難であり、またそのような中でも現に発症当月の2月4日と6日に医師を受診しているのである。労働者の自己保健義務違反による減額は、使用者である会社が法律で定められた健康診断やそれに基づく措置を十分に行い、また医師にかかる時間的余裕が現にあった場合に初めて問題とされるべきである。
このような理由で2割もの寄与度減額を行うことは、極めて不当といわなければならない。
この点、同種事案で平成13年3月9日になされた大阪地裁堺支部判決では、寄与度減額は一切認められていないことは注目すべきである。
これまで過労死の損害賠償請求事案では、裁判所は安易に寄与度減額や過失相殺を認める傾向にあったが、過労自殺についての電通事件最高裁判決(平成12年3月24日)は、「ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、・・・裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんしゃくすることはできない」として、過失相殺や寄与度減額を否定した。その結果、現在過労死事案と過労自殺事案で一種のずれが生じており、今後、この点に対する闘いが急務である。
(4)また、中間利息の控除率については、現在の金融事情のもとでは、多くても年1%程度とすべきである旨主張したが、判決はあっさり年5%でよいとした。
平成11年11月22日付で発表された東京・大阪・名古屋の各地裁の交通専門部による「交通事故による逸失利益の算定方法についての共同提言」では、「特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式を採用する」とされ、中路裁判長はその署名者の1人であったことから、この結果は予想されたものではあった。しかし、その後各地で4%、3%、2%などの判決が相次いでいる中で、なお「共同提言」に固執したことは問題といわなければならない。
とりわけ、共同提言は交通事故事案のための基準であり、労災事案については大量処理の要請もないのであるから、何の説得力もないものである。
3 闘いの展望
被告名糖運輸が控訴したため、西原さんも控訴し、大阪高裁で控訴審が闘われることになった。
なお、既に行訴の控訴審(大阪高裁民事13部)が3月28日に結審となる見通しであり、これも遺族側が勝訴すれば、最終的な勝利の展望は大きく開けることになろう。
弁護団及び支援の会は、2つの控訴審での闘いに全力を尽くす所存である。(弁護団は、山崎国満、坂本団、豊島達哉と私である。)
(民主法律時報346号・2001年3月)